「インターンのESすら通らない」、「自己分析はやってみたけど、ESへの落とし込み方がわからない」といった悩みを持った就活生の方は多いんじゃないんでしょうか!
筆者も就活生時代、なんとなく自己分析から始めたものの夏のインターン選考はESで全滅し、心も幻滅した過去がありました(やかましいですね)…
しかし秋から気持ちを入れ替え、構成と「ある軸」を意識してESを見直したところ、冬以降の選考ではES通過率80%、最終的にはみんなが名前くらいは知っている倍率100倍超えのエンタメ企業から内定をもらうことができました。
そこで初投稿となる今回は、”いざESを書き始めたけど書き方がわからない”という方向けに、通過するESの構成4つとそれぞれのポイントをお伝えします。
〜前準備〜 通過するESの構成を知るべし
自己分析が終わったら早速ESを書き始める人が多いのですが(筆者もそうでした)、ちょっと待ってください!
何事も効率よく質の高い結果を出すためには、まずゴールを知ることが大切です。ESの場合、この”ゴール”とは「正しい構成を知り、最低限入れ込む要素を選択すること」です。
これにより、文字数制限に合わせて加筆・削除を繰り返した結果イマイチ言いたい事がわからない志望動機が完成した、などのよくある失敗を避ける事ができるのです。
通過するESを書くために押さえるべき構成は4つです。
- 入社後やりたいこと/自己実現
- そう思うようになった背景/動機
- その会社である必要性/志望理由
- 自分がどう貢献できるか/強み
入社後やりたいこと/自己実現
入社後に実現したいキャリアビジョンを1文程度で伝えます。ここでのポイントは”簡潔さ”と”明確さ“です。ジャッジ側の選考官は1日で数百枚のESを読むので、つかみの部分で結論を提示してあげる必要があるのです。
余談ですが、学生さんのESをみると”重複する前置き”というのがよく見受けられます。
「弊社の志望理由を教えてください」という設問に対して、ファーストアンサーが「私が貴社を志望する理由は(以下続く)」で始まるような文章です。実はこの部分、設問を復唱してるだけで情報として新しい内容は全く無いんですよね。
こういった余分な部分も意外と気づかないモノなので、筆を動かす段階では情報として必要のない部分は無いか常に見直しを行いましょう!
そう思うようになった背景/動機
その目標を持つようになった原体験や価値観を伝えます。この部分は指定されている文字数の3~4割程度の分量で想定しておきましょう。学生時代・あるいは幼少期の経験や気づきを通して、なぜ冒頭のビジョンに至ったかを説明することで説得力を与えます。
ここでのポイントは”動機がスポットではなく中長期的に続いていることを示す“ことです。
きっかけとなる出来事に加え、それ以降も「御社を志望するまでモチベは鰻登りだよ〜」ということを示す事ができると、選考官に「この子は本当にここを志望してるんだな」という確信を持ってもらえるのです。
例えば、「幼少期に〇〇というゲームに没頭したのを機にゲーム業界に興味が湧きました!」という人より、「幼少期に〇〇をプレイしたのを機にゲームにハマり、その後△△や××にも触れて同好会まで立ち上げました!」という人の方が熱量が継続的ですし、主体的な行動にまで繋げていて本気度を感じませんか?
また、通過するESを書く上で最も重要と言える「差別化」を最も演出できるのがこの部分になるのですが、この「差別化」については本記事の後半で詳しく説明しますね!
その会社である必要性/志望理由
数ある企業の中で「なぜその会社なのか」を示しましょう。事業内容、社風、育成制度などに触れ、自分の目標との一致点や共感ポイントを具体的に伝えます。
分量は文字数制限にもよるのですが、だいたい全体の2~3割程度で想定しておくと良いでしょう。
この部分でのポイントは、”実現したいビジョンを叶える最適な場所が御社であるというストーリーを意識する“ことです。
ここだけの話、大義名分が無い限りだいたいの就活生は企業の社風や方針に寄せて志望動機を考えると思います。もともと大きな夢があって、それを叶えるために企業選びをするという方は稀でしょう。
しかし、その順番でESを書いていくとどうしても動機部分がとってつけた感じになり、印象に残らないテンプレ的なESが出来上がってしまいがちです。
内容構想段階では志望動機を企業に寄せていく考え方は必ずしも誤りではないのですが、実際に筆を動かす段階では「目的がビジョンで、そのための手段が御社に入ることなんです!」というストーリーに沿わせていくのがオススメです。
自分がどう貢献できるか/強み
これまでの経験から得た強みをもとに、会社にどう貢献できるかを伝えます。今までの部分では志望動機をアピールしてきたのに対し、この部分では「企業側があなたを採用するメリット」を示します。
ガクチカや自己PRを流用する方が多いと思うのですが、ポイントは”定量的な情報を盛り込む“ことです。
「順位を40位上げた」よりも「100人中70位だった順位が30位になった」の方が努力の規模がイメージしやすいですよね。
ESで最も意識すべき軸とは?
通過するESとそうで無いES、決定的な違いはなんでしょうか?
ガクチカの凄さでしょうか?
実は内容の質で両者に違いはほとんどありません。結果を分けているのは、”競合(=他の就活生)との差別化を意識できているか“です。
先ほども書きましたが、選考官は1日に数百枚のESに目を通し、そこから合否を振り分けていくわけです。当然1人のESを何度も読み返す時間はかけませんので、1回読んですんなり内容が入ってくる簡潔さは最低条件。さらに、倍率の高い難関企業の選考通過を目指すのであれば他の就活生のESと差別化できている事が望ましいでしょう。
では具体的にどのように差別化していくのか…という具体的な解説は今後単独で解説記事を出せればと思いますが、とにかく意識してもらいたいのは”ESの中で自分のアピールポイント(=戦う土俵)を明確に決めておく“という事です。
筆者的にオススメなのは、「動機」or「その会社である必要性」の部分をアピールポイントにする事です。「強み」の部分はよほど凄いガクチカでない限り、文章だけで差別化することが難しいからです。
アピールポイントの方向性としては以下のようなものがあります。
- 動機 →製品・サービスへの理解の深さ/エピソードのインパクト etc…
- 志望理由 →経営方針・業務理解の深さ etc…
まずはESの全体構成の中で、自分が1番企業にアピールできる要素はどれかをイメージしてから書き始めると方針のブレが最小限に抑えられますよ!
まとめ
今回は、通過する志望動機を書くための構成とそれぞれのポイントを解説しました。
ESを書き始める時は苦労するかと思いますが、おおまかな構成とそれぞれで意識すべきポイントがわかると書けそうだなと思えてきたのではないでしょうか。
ESは一旦書けば終わりではなく、幾つもの選考を通してブラッシュアップしていくものです。そのうち段々とクオリティの高い志望動機が書けるようになっていくので、都度このポイントを見直してみてくださいね!
それでは次の記事でまたお会いしましょう〜!
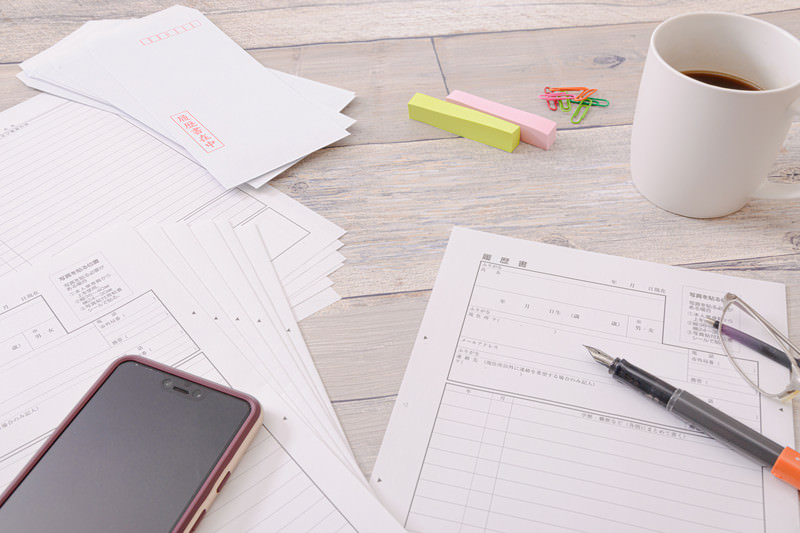
コメント